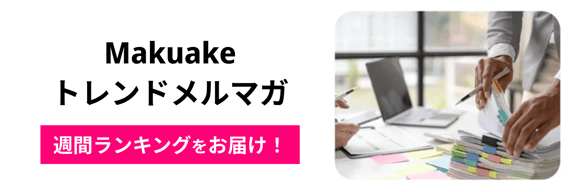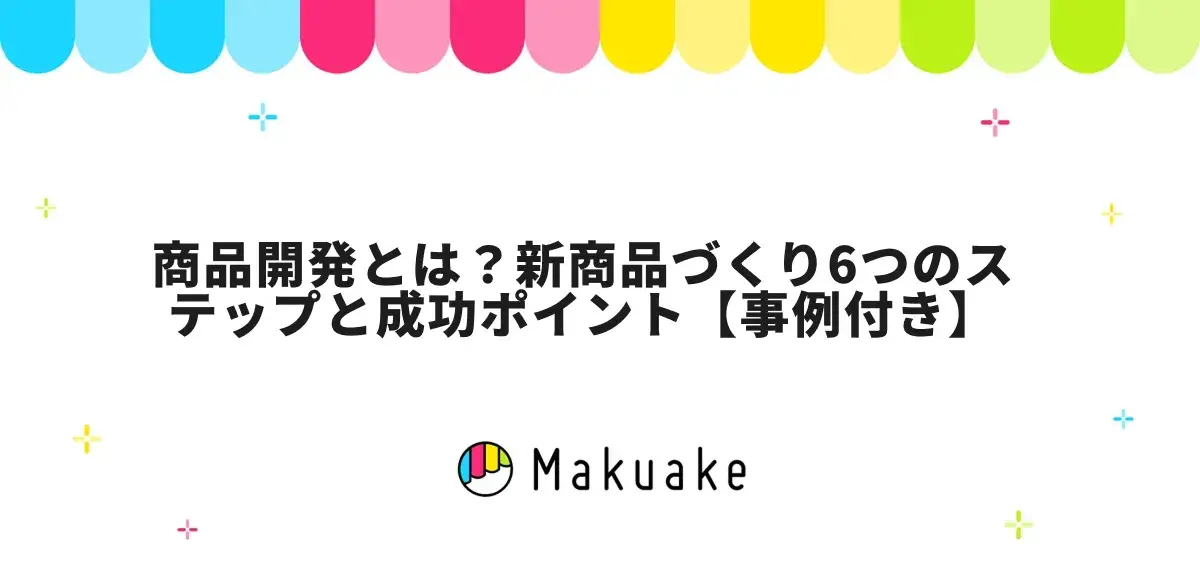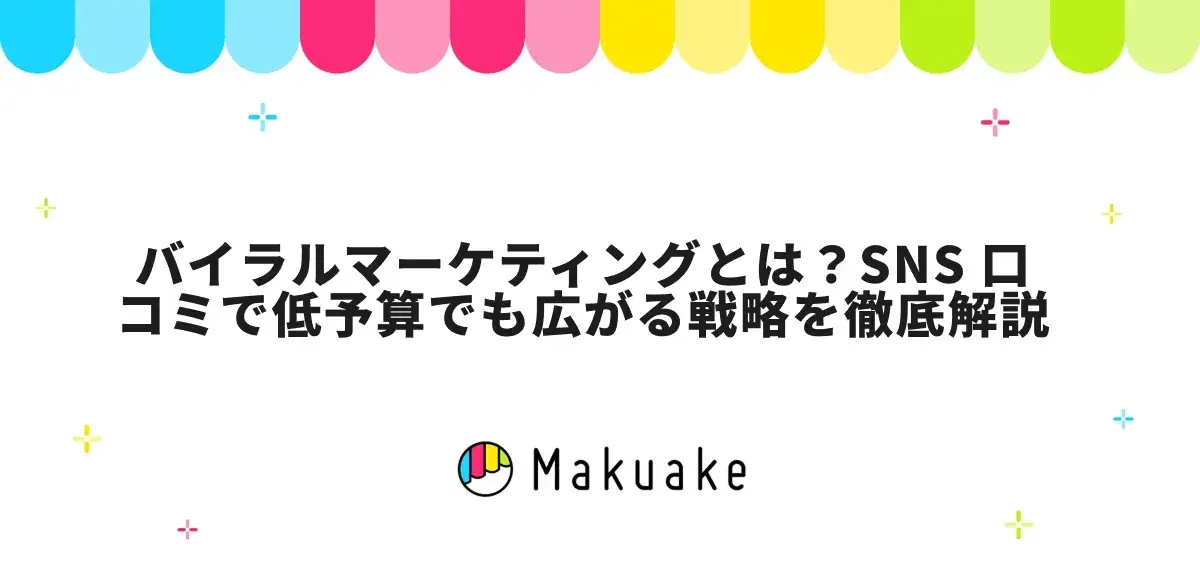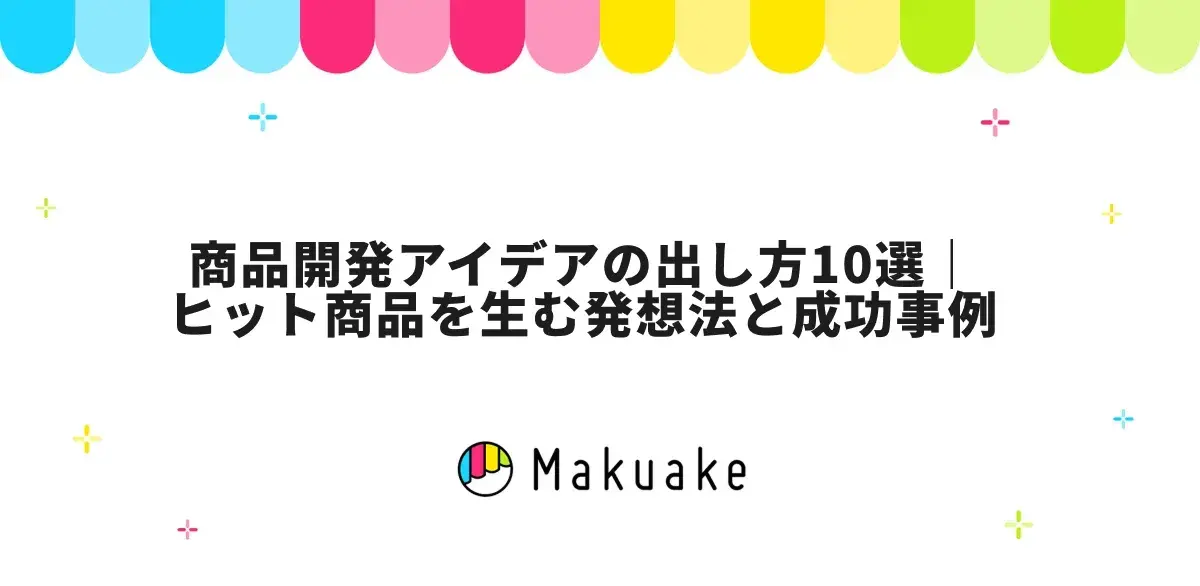下請けを脱却する方法とは?自社商品開発と販路拡大で高収益体質を作るには【事例あり】
アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」では購入型クラウドファンディングの特徴を活かしたテストマーケティングの事例が多くを占めています。特に注目されているのが、長年下請け企業として受注業務が中心だった中小製造業者が、独自商品の開発を通じて元請け企業へと転身するケースです。
「価格をもっと主導できれば…」「このまま親会社に依存していいのか…」と感じていませんか?
本記事では、下請けから脱却するための具体的な方法と成功のポイントを、実際の成功事例を交えながら解説します。概要から具体策、成功事例、そして実践のためのポイントまで網羅的にお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
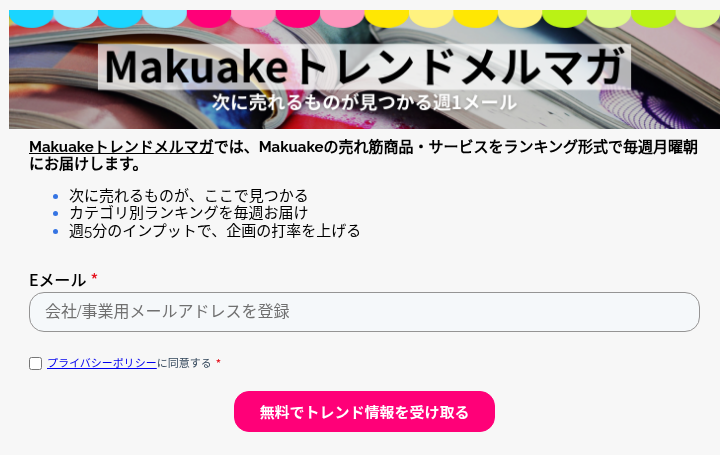
1) 下請けビジネスの現状と問題点

まず、下請けビジネスの現状を客観的に整理しましょう。下請けには確かにメリットもありますが、デメリットがあるのも事実です。
下請けビジネスのメリット
下請けビジネスには、以下のような利点があります。
【主なメリット】
- 安定した仕事量と収益源の確保:大企業が獲得した仕事を定期的に受注できるため、営業活動に時間を割かなくても一定の売上が見込める
- 特定分野での専門性向上:特定の技術や製品に特化することで、その分野における生産性や技術力を高められる
- 生産・開発コストの効率化:大量生産による規模の経済が働き、単位あたりのコストを抑えられる
- 大手企業の実績による信頼性向上:有名企業との取引実績が、自社の信用力向上につながる場合がある
これらのメリットにより、多くの中小企業が下請けビジネスを選択してきました。しかし、近年の経営環境の変化により、デメリットも顕在化しています。
下請けビジネスの問題点
2022年度に下請法違反に対する指導件数が8,665件と過去最高を記録し、その後も継続して高止まりしている傾向です。この数字が示すように、下請けビジネスには不公正な取引や要求がなされる場合も少なくありません。原材料費や人件費の高騰に対して、元請けからの値下げ圧力が強まり、利益が圧迫されているケースが確かに存在しています。
【下請けビジネスの主要な問題点】
|
問題点 |
具体的な影響 |
リスクレベル |
|
取引先依存によるリスク |
売上の70%以上を1社に依存→連鎖倒産の危険性 |
高い |
|
価格交渉力の欠如 |
元請けからの一方的な値下げ要求→利益率の低下 |
高い |
|
自社ブランドの不在 |
技術力があっても表に出ない→成長機会の喪失 |
中~高 |
|
中間マージンの搾取 |
多重下請け構造による利益の目減り |
高い |
|
イノベーションの停滞 |
仕様通りの製造に終始→新規開発力の低下 |
中程度 |
特に深刻なのは、親会社の業績悪化に伴う連鎖倒産のリスクです。実際、製造子会社による不当な負担強要など、大手企業による「下請けいじめ」のニュースは頻繁に発生します。このような状況下で、「下請け企業として受注のみに依存していると、この先生き残れないかもしれない」という危機感を持つ経営者が増えているのです。
2)下請けから脱却することのメリット

では、下請けから脱却すると、どのような未来が待っているのでしょうか。脱却によって得られるメリットは、想像以上に大きなものです。
収益性の劇的な改善
脱下請けの最大のメリットは、収益性の改善です。自社製品を直接販売することで、これまで手にすることができなかったマージンを自社の利益とすることもできます。
ある町工場では、自社開発製品によって粗利率が25%から45%に改善し、売上は5倍に成長しました。これは決して特殊な例ではありません。中間マージンを省いて高い利益率を実現でき、価格競争にも陥りにくくなるのです。
経営リスクの分散と安定性向上
取引先を複数に分散することで、一社依存のリスクから解放されます。仮に一社との取引が途絶えても、会社全体が傾くリスクを大幅に軽減できるのです。
実際、脱下請けに成功した企業の多くは、取引社数を10倍以上に増やしています。これにより、経営の安定性が飛躍的に向上し、長期的な成長戦略を描けるようになります。
価格交渉力と市場での主導権獲得
自社が元請けだけではなくエンドユーザーと直接取引すれば、価格決定権を握れるようになります。「言われたままの価格」から脱却し、自社の提供価値に見合った価格を提示・交渉できるようになるのです。
さらに、自社ブランド製品がヒットすれば市場での認知度が上がり、新たな顧客を呼び込む好循環が生まれます。金融機関からの評価も高まり、融資など資金調達が有利になる可能性もあります。
3)「脱下請け」が難しい理由と乗り越えるべき課題

下請け企業が元請け企業に転換するメリットを理解しても、「とはいえ現実には難しいのでは?」という不安を抱く方もいらっしゃるかと思います。確かに、多くの企業が脱下請けに苦戦しているのも事実です。しかし、課題を明確化することで、解決への道筋が見えてきます。
営業力・マーケティング力の不足
長年、元請けからの仕事を受注してきたため、自社で新規顧客を開拓する営業スキルや習慣が乏しい企業も多いです。毎月安定した受注があると、新規開拓の意欲が薄れるのも無理はありません。
また、独自に市場展開するには、客観的なデータ分析や市場ニーズの把握が必要ですが、それが不足している企業も少なくありません。技術はあっても「何が求められているか」を見極めれなければ、良い技術があっても市場価値の高い製品を作るのは難しいです。
リスクを恐れる企業文化と経営資源の制約
下請けで安定収入が得られている現状から抜け出すには相応のリスクが伴います。経営者自身に挑戦意識が不足していたり、社内が保守的で新しい試みに消極的だったりすることも大きな障壁となります。
さらに、新規事業や自社製品開発には資金や人材、時間が必要ですが、中小企業ではそれらが限られているため二の足を踏むケースも多いのです。仮に経営者がやる気でも、従業員の意識改革が追いつかず、生産現場が混乱するリスクもあります。
しかし、これらの課題は克服不可能なものではありません。次では、これらの課題を乗り越えるための具体的な戦略を詳しく解説します。
4)下請け脱却のための戦略とステップ

いよいよ、脱下請けを実現する具体策について解説します。一度に全てを変える必要はありません。段階を追って実施していくことが成功の鍵です。
現状分析と戦略立案:市場を把握し自社の戦い方を決める
まず最初に取り組むべきは、自社と市場を知ることです。自社や元請け企業の視点だけではなく、業界全体のトレンドやエンドユーザーなど、自社に関わる広いステークホルダーのニーズに目を向けることが大切です。
【市場環境の調査方法】
- 中小企業庁や業界団体の公開データを活用し、市場規模や成長率をチェック
- インターネットや業界紙、図書館の市場レポートで競合他社の動きを把握
- 展示会やセミナーに参加し、最新のトレンドを収集
同時に、自社の強み・弱みの洗い出し(SWOT分析:自社の強み・弱み・機会・脅威を整理する手法)も行います。社員から最低10個ずつ自社の強みアイデアを出してもらうと、意外な視点から、強みが見つかることもあります。
ここで重要なのは、戦略目標を明確にすることです。
例えば「5年後に下請け依存度を20%以下にする」「○○分野で年商3億円を達成する」など、具体的な数値目標を設定しましょう。いきなり下請けをゼロにする必要はなく、既存の安定収入を維持しつつ徐々にシフトするのも現実的な戦略です。
独自商品の開発・サービス化:自社の強みを形にして提案力を高める
戦略が定まったら、次は自社オリジナルの商品やサービスを開発する段階です。ただし、闇雲に新商品を作るのではなく、必ず市場のニーズと自社の強みの交差点を探します。「誰のどんな困りごとを解決できるか?」を出発点に企画することが大切です。
【商品開発のステップ】
- ニーズ発見型の商品企画:顧客の課題×自社の技術=新商品
- プロトタイプ(試作品)の開発:最初から完璧を目指さず、少量生産でテスト
- テストマーケティング:クラウドファンディングの仕組みをつかって市場の反応を確認
特に注目すべきは、クラウドファンディングの仕組みを活用することです。この仕組みを活用すれば、テストマーケティングとして少ないコストで市場の反応を試せる上に、資金も集められます。
実際、木製品メーカーが培った加工技術で高級文具を開発したり、自動車部品メーカーが照明技術を応用して一般消費者向けのインテリア照明を開発したりといった成功例が多数、存在します。商品だけでなく、設計力を活かしたコンサルティングサービスの提供という選択肢を選ぶ企業もあります。
関連記事:プロトタイプとは? Web・製品開発での意味と作り方を5ステップで解説
Makuakeトレンドメルマガでは、Makuakeの売れ筋商品・サービスをランキング形式で毎週月曜朝にお届けします。ぜひ、このメールマガジンを貴社の商品開発や出店・出品計画の参考情報としてお役立てください。
【このような方におすすめ】
・新商品を販売開始する前に、Makuakeのトレンドを理解したい方
・季節やニーズのトレンドを商品開発やマーケティングに役立てたい方
新規顧客の開拓:販路拡大とマーケティング戦略の実践
良い商品・サービスを開発しても、それを買ってくれる顧客を獲得しなければ脱下請けは実現しません。集客は、多くの企業にとって顧客獲得の最大の障壁となる場合が多く、適切な対策が必要です。
オンライン施策(ホームページ・メディア・SNS)
ホームページは24時間働く営業マンです。まだホームページをお持ちでない場合は、簡単なもので構わないので開設をおすすめします。会社概要だけでなく、自社の強みや事例、お客様の声なども掲載できると信用力が増します。
さらに、自社の専門知識を発信するブログ(オウンドメディア)を作り、読者との信頼関係を築く手法も有効です。SNSは無料で始められる広報ツールであり、特に一般消費者向けビジネスならInstagramやX(旧Twitter)で商品の魅力や開発秘話を発信するとファン獲得につながります。
オフライン施策(展示会・DM等)
業界の展示会に試作品を出して反応を見るのも有効です。共同出展などコストを抑える方法もあります。展示会では製品そのものより自社の技術力をPRすることがポイントです。「うちには完成品がない…」という場合でも、技術デモやパネル展示で「何ができる会社か」を訴求すれば、協業や発注の話が持ち上がる可能性があります。
自社に合った手法を選ぶことが大切です。一度に全ては難しいので、できるものから順番に試すことをおすすめします。
問い合わせ件数を月○件増やすなど、具体的な目標設定をすると計画が回しやすくなります。集客は継続が命です。一度で結果が出なくてもPDCAを回してブラッシュアップしていくことが可能です。
経営資源の確保:資金調達と人材育成で挑戦を支える
新規事業展開には資金と人材が必要です。脱下請けの取り組みを下支えするための経営資源の確保策を整理します。
【主な資金調達手段】
|
調達方法 |
メリット |
注意点 |
適用場面 |
|
銀行融資 |
大規模な資金調達が可能 |
事業計画書・自己資金が必要 |
設備投資・運転資金 |
|
公的補助金 |
返済不要・採択率が比較的高い |
申請手続きが複雑 |
新製品開発・販路開拓 |
|
クラウドファンディングの仕組み |
資金調達+市場テストが同時に可能 |
事前告知・リターン設計が重要 |
B2C商品開発 |
特に注目すべきは事業再構築補助金など、下請けからの事業転換を支援する大型補助金です。また、クラウドファンディングの仕組みを活用して資金を集めながらプロモーションするという一石二鳥の方法も有効です。
人材面では、必要に応じてプロ人材の力を借りる手もあります。マーケティングスキルが不足しているなら、専門家を招いた勉強会を開く方法もあります。無料ウェビナーや地域の支援機関のセミナーなど負担が少なく参加できるものもあります。
新たな挑戦を成功させるためには、資金と人材という基盤を固めることが大切です。
関連記事:中小企業がクラウドファンディングで資金調達!成功するためのポイントとは
外部パートナーとの連携:協業や支援機関を活用し一社でできないことを補う
脱下請けは自社単独で完遂する必要はありません。外部の力も活用できます。
脱下請けを目指す企業同士で情報交換すれば、有益なヒントが得られます。業界団体や勉強会に参加してネットワークを広げるのもおすすめです。
また、専門家に相談することも重要です。地域のよろず支援拠点や商工会議所の経営相談など、無料で利用できる公的相談窓口もあります。
専門家に話すことで自社を客観視でき、意外と早期に解決策が見つかることもあります。コンサルタントを活用することで補助金情報や他社連携の機会も得られる可能性もあります。
関係性のよい元請け企業とは、ビジネスパートナーへ関係を変化できないか打診する方法もあります。例えば共同開発を持ちかける、価格決定に貢献することでマージンを見直してもらうなどが考えられます。交渉時はWin-Winになる提案を心がけ、会社の外にも目を向けると道が拓けることがあります。
社内体制の整備:社員の意識改革と組織づくりで持続可能な変革へ
新しい挑戦を成功させるには、社内の協力が不可欠です。必要な場合は社員全員を巻き込む意識改革を行います。
まず社長自身が脱下請けへの覚悟を示すことが大切です。全社集会などで「新規事業を必ず成功させる」と宣言し、具体的な目標(新規取引○件獲得など)を社員と共有することが効果的です。
【社内体制整備のポイント】
- 経営者の覚悟表明:トップの本気度を社員に示す
- 目標の社内共有:数値目標を明確化し、全員で追う
- 新体制の構築:プロジェクトチームなど部署横断の取り組み
- 社員研修と手順整備:新業務に対応できる体制づくり
- 挑戦を称える社風づくり:成功を皆で祝い、失敗は皆で改善
既存業務との両立が必要になるため、現場の負荷にも配慮が必要です。まずは小規模に始めて、問題点を洗い出しながら進めます。下請け中心だった社員にとっては戸惑いも大きいかもしれません。新しい業務手順や顧客対応については、OJTやマニュアル整備でしっかりサポートします。
経営者が率先垂範する姿勢が社員の意識を変えます。トップ自ら営業に出向いたり、新商品のアイデアを出したりすることで、社員も「本気なんだ」と感じ、力を貸してくれるでしょう。社内が一丸となれば、脱下請けへの挑戦はきっと実を結びます。
5)脱下請け成功事例:自社ブランド立ち上げに成功した町工場のケース

ここで、実際に脱下請けに成功した企業のもう一つの例を紹介しましょう。福井県鯖江市の眼鏡部品メーカー、株式会社西村プレシジョンのケースは、多くの製造業の方にとって参考になるはずです。
西村プレシジョン社の挑戦:下請けからの脱却を決意

眼鏡の聖地・鯖江で創業した西村プレシジョン社は、従来は国内外の大手ブランドの部品製造を請け負う下請けメーカーでした。しかし、西村社長は「産地の技術力は世界一なのに、下請けのままでは未来がない」と強い危機感を抱き、自社ブランド製品の開発への挑戦を開始しました。
彼らが目を付けたのは、自社の強みである精密金属加工技術を活かした独自の老眼鏡です。社長自身が感じていた「必要な時にすぐ見つからない」「持ち運びが不便」という老眼鏡への不満を解決するため、「紙のように薄く、携帯性に優れた老眼鏡」という全く新しい発想で開発した「ペーパーグラス」は、まさに自社の技術力と課題解決のアイデアを結晶させた商品で、そのデザイン性と機能性が高く評価され、グッドデザイン賞BEST100をはじめ、国内外のデザイン賞を次々と受賞。
Makuakeでのテストマーケティングの成功と事業転換

この画期的な商品を世に広めるにあたり、西村プレシジョン社はMakuakeで新モデルの先行販売を実施しました。その結果、製品のコンセプトは多くの支援者の共感を呼び、プロジェクトは大成功を収めました。
製品は正式に市場投入され、ドイツのiFデザイン賞も受賞。発売から数年で累計数十万本を販売する大ヒット商品となり、同社はこれをきっかけに劇的な事業転換に成功します。
「ペーパーグラス」の成功後、同社は下請け中心の事業から自社ブランドを核とするメーカーへと変貌を遂げ、国内外に直営店を展開するまでに成長しました。さらに第二弾、第三弾として軽量化した「ペーパーグラス・ライト」や「ペーパーグラス・サングラス」など、顧客のニーズを捉えた新商品を次々と開発・投入し、ブランドを拡大し続けています。
成功要因の分析
西村プレシジョン社の成功要因を整理すると、以下の3点が挙げられます。
- 自社の高い技術力を活かし、経営者自身の原体験から生まれた商品を見つけたこと
- Makuakeでのテストマーケティングで資金と熱心な初期顧客の獲得に成功したこと
- デザイン賞の受賞などを通じてブランド価値を高め、継続的に新商品を開発したこと
このケースが示すように、地方の中小企業でも自社の技術とアイデアを組み合わせれば、世界に通用するブランドを創り出せるのです。鯖江の老舗部品メーカーが成し遂げたこの事実は、同じ課題を抱える多くの下請け企業にとって大きな励みとなるでしょう。
6) まとめ:下請け脱却に向けて今日からできること

本記事では、下請け脱却のポイントを以下の流れで解説してきました。
【下請け脱却の6つのステップ】
- 市場を分析し、自社の強みを把握する
- 独自商品・サービスを開発する
- 新規顧客を開拓する
- 資金・人材を確保する
- 外部パートナーと連携する
- 社内体制を変革する
一度に全てを行う必要はありません。できることから一歩ずつ取り組むことが重要です。脱下請けは短期で劇的に成果が出るものではないかもしれません。しかし、小さな成功と失敗を積み重ねることで必ず前進できます。
下請け脱却は一朝一夕にいくものではありませんが、必ず達成できます。
応援購入サービスMakuakeの活用もご検討ください
私たちMakuakeは、挑戦する中小企業を応援しています。応援購入サービスをテストマーケティングで活用することで、低リスクで市場に挑戦できます。当社では多くの中小企業の新規事業をサポートしてきました。
自社商品開発やテストマーケティングに興味があれば、ぜひお気軽にご相談ください。商品のブラッシュアップや市場テストなど、お悩みがあればサポートさせていただきます。
 By
By