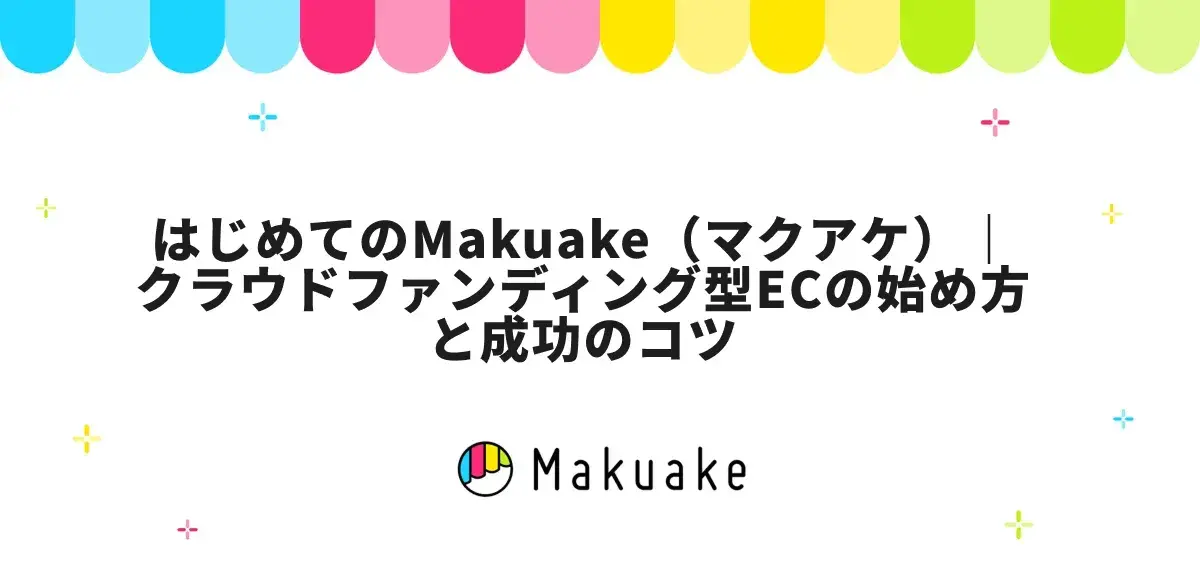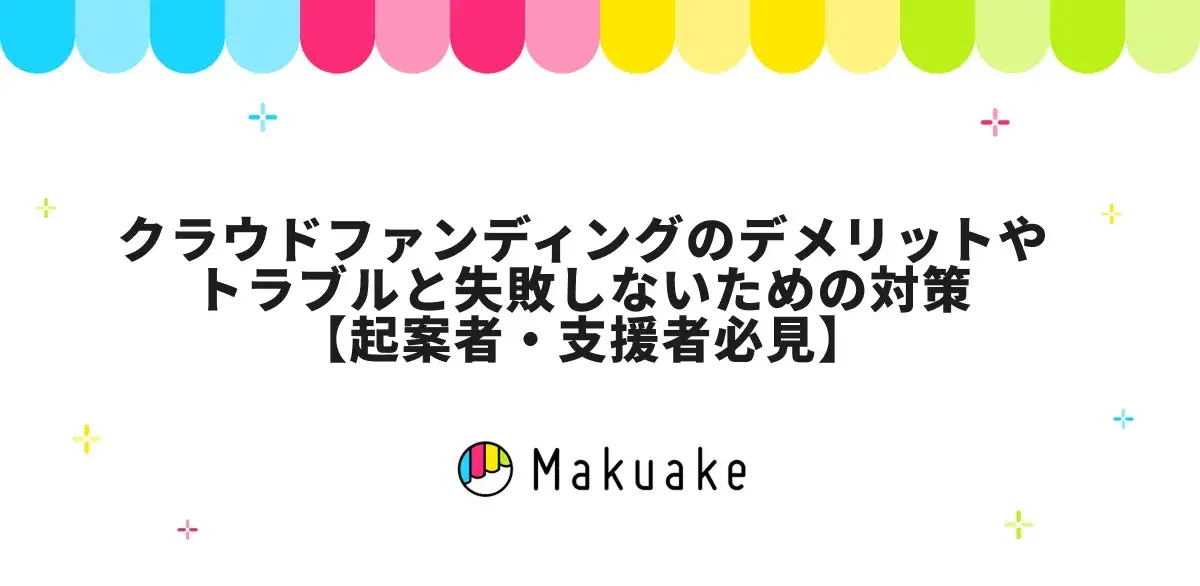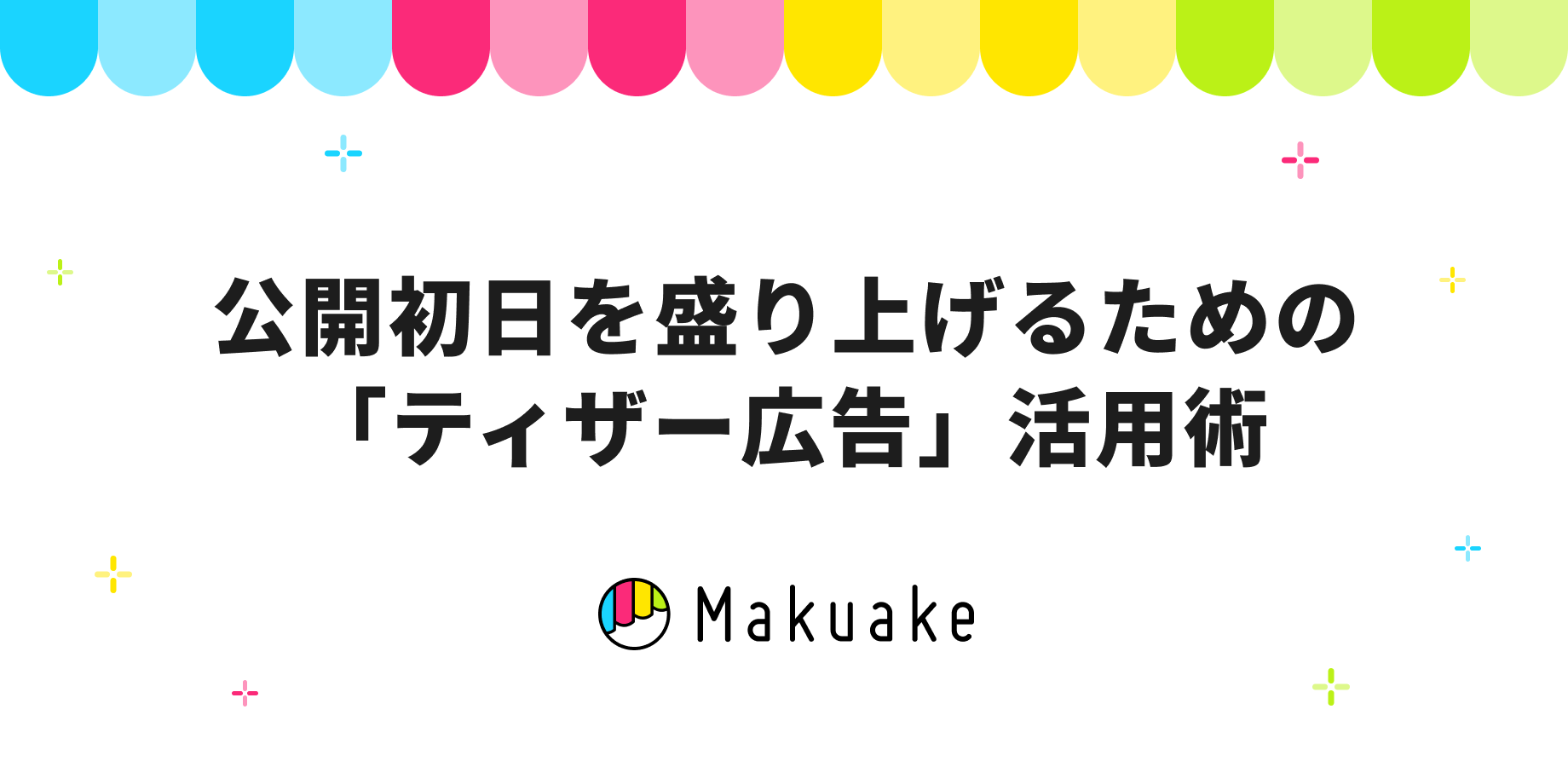クラウドファンディングの宣伝方法とは?|15の打ち手と成功事例
クラウドファンディングの宣伝方法について、「毎日SNSで発信してるのに、プロジェクト公開したら支援者が増えない…」といった悩みをお持ちの起案者の方も多いのではないでしょうか。
どれほど魅力的な商品やサービスを生み出しても、人に知ってもらわなければその価値は伝わりません。
実際、目標金額を大きく上回る支援を集めるプロジェクトと、目標未達に終わるプロジェクトの最大の違いは「宣伝戦略の有無」にあります。
「何から手をつければいいかわからない」「広告費をかけずに成功させたい」「失敗したくない」——多くの起案者がこうした悩みを抱えています。
この記事では、クラウドファンディングの宣伝について、いつ・何を・どのように行うべきか、準備期から終了後まで、プロジェクトのフェーズごとに実践すべき15の打ち手を具体的なアクションプランと成功事例を交えて徹底解説します。
(※)プラットフォームにより、「起案者」はプロジェクトオーナー、実行者、クリエイターなど、「支援者」は、サポーターやバッカー、応援者などさまざまな呼び方で表現されます。この記事では代表的な表現である「起案者」、「支援者」を採用しています。
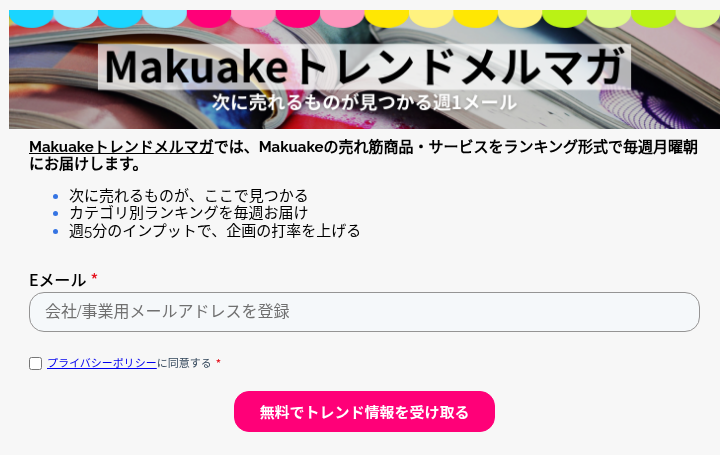
1)宣伝を始める前に知るべき!クラウドファンディング宣伝 3つの成功原則
2)クラウドファンディングの宣伝はいつから? フェーズ別アクションプラン
3)ロケットスタートを決める!公開前にやるべき7つの宣伝方法
4)支援の勢いを加速させる!期間中にやるべき5つの宣伝方法
1)宣伝を始める前に知るべき!クラウドファンディング宣伝 3つの成功原則

具体的な宣伝手法に入る前に、プロジェクトを成功に導くための考え方を理解しておきましょう。
原則1:プロジェクトの宣伝にかかるリソースを把握する
プロジェクトの宣伝・運営には、人手や時間、資金などのリソースが必要です。
プロジェクト実施中に本業が忙しくなり人手が割けなくなる、SNSの運用が疎かになる、問い合わせ対応に時間がかかりすぎるといった事態が起きると、伸びるはずのプロジェクトも中途半端に終わってしまいます。
特に公開直後の「初速期」には集中的にリソースを投下できるよう、計画的に準備を進めましょう。
原則2:初速で8割が決まる
クラウドファンディングでは、プロジェクト公開から当日〜3日の「初速期」が極めて重要です。公開直後に目標達成の勢いを見せると「バンドワゴン効果」が働き、サイト内の注目位置に掲載され、さらなる流入が生まれます。
金額設定を踏まえた時間軸の理解も重要です。目標金額が100万円でリターンの平均単価が1万円の場合、100人の支援者が必要です。
プロジェクトページの閲覧から支援までの転換率が一般的に5〜10%程度とすると、1,000〜2,000人にページを見てもらう必要があります。
この数字から逆算して、どの宣伝手法にどれだけのリソースを投下すべきかを戦略的に考えることが重要です。
原則3:「ファン」を作る意識で丁寧なコミュニケーションを心がける
SNSアカウントやプロジェクトページを使った情報発信や、応援メッセージへの返信はこまめに行うようにしましょう。新着情報の発信、プロジェクトの進捗、プロジェクトへの思い、商品・サービスに関するお知らせなど、些細なことでもいいので、定期的に情報発信やユーザーとのコミュニケーションを取ることが大切です。
単なる支援者ではなく、長くブランドを支えてくれる「ファン」として、丁寧かつ迅速な対応を行うことが肝心です。
2)クラウドファンディングの宣伝はいつから? フェーズ別アクションプラン

宣伝活動は、プロジェクト公開の瞬間から始まるわけではありません。
成功するプロジェクトは、公開の数週間〜1ヶ月前から綿密な準備を行い、公開後も継続的に活動を続け、さらに終了後もファンとの関係を深めています。
ここでは、プロジェクト全体を3つのフェーズに分け、それぞれで実施すべき宣伝活動の概要を示します。
【準備期(公開〜1ヶ月前)】初速を最大化する仕込みの期間
準備期は、プロジェクト成功の基盤を作る最も重要な期間です。この期間にやるべきことは以下の通りです。
- SNSアカウントの開設とフォロワー獲得の開始
- プレスリリースの準備とメディアリスト作成
- ティザーサイト(LP)での事前告知とメールリスト獲得
- 友人・知人など「最初の応援団」への事前告知
- 関連コミュニティへの参加と貢献
- インフルエンサーへの事前アプローチ
- 心を掴む宣伝素材(画像・動画)の準備
この期間の目標は、公開と同時に「待ってました!」と支援してくれる人を一定数確保することです。初速を確実にするための仕込みに全力を注ぎましょう。
【公開中】熱量を維持し支援を加速させる期間
プロジェクト公開後は、初速の勢いを維持しながら、継続的に新規支援者を獲得していく期間です。
- SNSでの日々の活動報告と進捗シェア
- プレスリリースの配信(スタート時・中間達成時など)
- Web広告の活用(SNS広告・リターゲティング広告)
- 支援者コメントへの返信と活動報告での交流
- 追加リターンやキャンペーンによるテコ入れ
プロジェクト公開直後は支援が集まりやすいものの、日々多くのプロジェクトが公開されていく中で、日数が経過するにつれてページを閲覧する人が減ることが多々あります。継続的な露出とエンゲージメント向上の施策が不可欠です。
【終了後】ファンとの絆を深め、次につなげる期間
プロジェクトは目標達成で終わりではありません。支援者をファン化し、次のプロジェクトや事業につなげるための重要な期間です。
- 全支援者への感謝のメッセージ
- リターン発送までの定期的な進捗報告
- SNSやメルマガでの継続的な関係構築
この期間を丁寧に過ごすことで、支援者は単なる購入者ではなく、あなたのブランドや活動を応援し続けてくれる「ファン」へと変わっていきます。
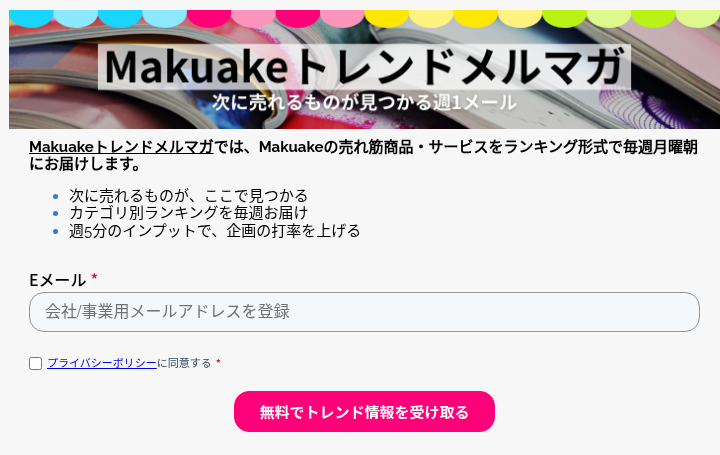
3)ロケットスタートを決める!公開前にやるべき7つの宣伝方法

プロジェクトの成否を分ける最も重要なフェーズが準備期です。
ここでの仕込みの質が、公開後の初速を決定づけます。
SNSアカウントの開設とファン作り
プロジェクト公開の1ヶ月以上前に、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなどの主要SNSアカウントを開設し、定期的な投稿を開始しましょう。
プロジェクトの開発ストーリー、商品へのこだわり、チームの日常などを発信し、公開前からファンを獲得することが大切です。
各SNSは特徴やターゲット層が異なります。投稿内容がプロモーション一辺倒にならないよう、ストーリーや共感を生む内容を心がけることがポイントです。
SNS広告を利用する場合は月1〜10万円程度の予算を見込んでおくとよいでしょう。
プレスリリースの準備とメディアリスト作成
プロジェクトに関するプレスリリースを事前に準備し、公開後に速やかに配信できる状態にしておきます。また、自社のプロジェクトが掲載されるとより反響が出そうなメディアのリストを作成し、個別アプローチの準備も進めておきましょう。
メディアが取り上げたくなるような「新しさ」「社会性」「ユニークさ」を明確に打ち出すことが成功のコツです。
「PR TIMES」などのプレスリリース配信サービスを活用すると、より多くのメディアに一挙にアプローチできます。
ティザーサイト(LP)での事前告知とリスト獲得
プロジェクト専用のティザーサイト(LP)を作成し、「近日公開予定」として情報を小出しにしながら、メールアドレス登録やLINE登録をしてもらう仕組みを構築しましょう。
このリストが、公開時の初速を支える重要な資産となります。
登録者限定の特典(早期支援者割引、限定リターンなど)を用意すると、登録率が大幅に向上します。
友人・知人など「最初の応援団」への事前告知
身近な友人・知人、職場の人、家族などに、SNSの発信などを通じてプロジェクトを実施していることを伝えましょう。
なぜこのプロジェクトを実施するのかという意気込み、未来への展望、そして御礼の気持ちを丁寧に伝えることが大切です。
公開と同時に支援してもらうだけでなく、SNSでのシェアなど、拡散にも協力してもらえるよう事前にお願いしておくと効果的です。
より多くの人からの応援と共感を生み出すためには、身近な人に自信を持っておすすめできるプロジェクトであることが欠かせません。
インフルエンサーへの事前アプローチ
自社のプロジェクトと親和性の高いインフルエンサーをリストアップし、公開前に商品サンプルを送付したり、プロジェクトの背景を説明したりして、公開時に紹介してもらえるよう交渉します。
有名なインフルエンサーであれば誰でも良いわけではありません。
自身のプロジェクトとの親和性が低いインフルエンサーを起用してしまうと、魅力が十分に伝わらなかったり、PR感が強くフォロワーに煙たがられる可能性もあります。
フォロワー数万〜数十万というマイクロインフルエンサーの方が、エンゲージメント率が高く、費用対効果が良い場合もあります。
著名でフォロワー数の多いアカウントであればあるほど依頼料が高額になるケースがほとんどですので、依頼するインフルエンサーは慎重に選定するようにしましょう。
心を掴む宣伝素材(画像・動画)の準備
プロジェクトページやSNS、広告で使用する高品質な画像や動画を事前に準備します。商品の魅力が一目で伝わるビジュアル、使用シーンがイメージできる動画などは、支援率を大きく左右します。
予算が許す限り、プロのカメラマンや動画クリエイターに依頼することをおすすめします。素材の質が支援率に直結するからです。単なる商品紹介ではなく、開発ストーリーや想いが伝わる内容にすることで、共感を生みやすくなります。
写真撮影で数万円、動画制作で数十万円程度の費用が一般的です。画像や音声などからブランドや商品の世界観がより伝わりやすく、アパレルやフード、ジュエリーなど形があるものとは相性がいいと言われています。
4)支援の勢いを加速させる!期間中にやるべき5つの宣伝方法

プロジェクトが公開されたら、初速の勢いを維持しながら、継続的に新規支援者を獲得していく必要があります。
SNSでの日々の活動報告と進捗シェア
プロジェクトの進捗状況(達成率、支援者数の増加、メディア掲載など)を日々SNSで報告します。「目標金額の50%達成!」「支援者100名突破!」といった節目ごとに投稿し、盛り上がりを可視化しましょう。
数字だけでなく、グラフや画像を使って視覚的に進捗を伝えると効果的です。支援者への感謝のメッセージを必ず添えることで、コミュニティの一体感が生まれます。「シェアして応援してください!」と明確にお願いすることで、拡散率が高まります。
投稿頻度が高すぎるとフォロワーに煙たがられる可能性があるため、1日1〜2回程度を目安にしましょう。この施策は無料で実施できるため、コツコツと継続することが大切です。
プレスリリースの配信(スタート時・中間達成時など)
プロジェクト公開時、目標金額達成時、大きな節目(支援者1,000名突破など)のタイミングでプレスリリースを配信します。メディアは「今起きていること」に関心が高いため、タイムリーな配信が重要です。
達成の瞬間を逃さず、迅速にリリースを配信しましょう。「公開3時間で目標達成」「支援総額が○○万円を突破」など、具体的な数字を盛り込むことでニュース性が高まります。
配信サービス利用で費用がかかりますが、記者がニュースのネタを探す際にも活用されており、プレスリリースをもとに記事化されたり、取材依頼がくるケースもあります。
Web広告の活用(SNS広告・リターゲティング広告)
Web広告を活用して、より多くの潜在支援者にリーチします。
特に効果的なのは、一度プロジェクトページを訪問したユーザーに継続的に広告を表示させるリターゲティング広告や、興味関心の近いユーザーに表示されるSNS広告です。
Web広告はユーザーの年齢や性別、地域や興味関心、普段どのようなキーワードで検索しているかなど、さまざまな観点からターゲットを絞り込むことが可能です。より自社のプロジェクトに興味を持ってくれそうなユーザーに対して自社の情報を届けることができます。
複数の広告素材を用意し、どれが最も効果的かをテストしながら運用することがポイントです。30万円程度の予算を見込んでおきましょう。
支援者コメントへの返信と活動報告での交流
支援者からのコメントや応援メッセージには、必ず迅速かつ丁寧に返信します。
また、プロジェクトページの活動報告機能を使って、開発の進捗や裏話などを定期的に投稿し、支援者との交流を深めましょう。
テンプレート的な返信ではなく、一人ひとりに向けた個別のメッセージを心がけることで、支援者は「大切にされている」と感じます。活動報告は週1〜2回程度の更新が理想的です。
返信が遅れると不信感につながる可能性があるため、24時間以内に返信するよう心がけましょう。この施策は無料で実施できますが、時間と労力が必要になります。
追加リターンによるテコ入れ
プロジェクト中盤で勢いが落ちてきたら、追加リターンの投入を実施し、再度注目を集めることも可能です。「先着50名限定」「残り48時間限定」など、希少性を強調することで購買意欲を刺激します。追加リターンは、SNSなどで積極的に告知しましょう。
5)プロジェクト終了は終わりじゃない!ファン化を促進する3つのアクション

プロジェクトが目標金額を達成して終了しても、起案者の仕事は終わりではありません。むしろここからが、支援者を「ファン」に変えていく重要な期間です。終了後の丁寧なコミュニケーションが、次のプロジェクトや事業の成功につながります。
全支援者への感謝を伝える
プロジェクト終了直後に、すべての支援者に対して感謝を伝えます。
プロジェクトページの活動報告を通じて、「あなたの支援があったからこそ、プロジェクトが成功しました」という気持ちを伝えましょう。
「皆様のおかげで目標金額の200%を達成できました」「○○名の方にご支援いただきました」など、具体的な数字とともに感謝を伝えます。今後のスケジュールや、リターン発送までの流れを明確に伝えることで、支援者の不安を解消できます。
リターン発送までの定期的な進捗報告
リターンの製造状況、発送準備の進捗などを、定期的に活動報告を発信します。
製造の遅れなど、ネガティブな情報だとしても、正直に伝えることで、信頼関係が深まります。製造現場の写真や動画を共有することで、支援者は「自分が支援したプロダクトが形になっていく」過程を楽しめます。
SNSやメルマガでの継続的な関係構築
リターン発送後も、SNSやメルマガを通じて支援者との関係を継続します。
商品の使用方法の紹介、ユーザーの声の共有、新商品の開発状況など、ファンが喜ぶコンテンツを定期的に発信しましょう。
6)Makuakeの成功プロジェクトに学ぶ! 「勝つべくして勝つ」戦略

理論を実践に移すために、Makuakeで大きな成功を収めたプロジェクトの宣伝戦略を分析してみましょう。これらの事例から、あなたのプロジェクトに活かせるヒントを見つけてください。
事例1:宣伝計画を立てて実行することで財布を500万円販売に成功した宇内金属工業
基本情報
- 支援総額:500万以上
- 支援者数:700人以上
- プラットフォーム:Makuake
成功の要因分析
金属加工と革加工の独自技術を持つ宇内金属工業は、キャッシュレス時代のニーズに合ったリニューアル製品の認知獲得と販売実績づくりを目的としてMakuakeを活用しました。
成功の最大の要因は、Makuake担当キュレーターとの二人三脚による、戦略的な広告宣伝計画の実行にありました。キュレーターは、ノウハウやリソースが不足する実行者に対し、「初日でこの金額、次はここまで」といった具体的なマイルストーンを設定し、プロジェクトの実行確度を高めました。
また、商品の魅力の伝え方やリターン設定の工夫に加え、InstagramやLINEといったSNSの具体的な活用方法に関する実践的なアドバイスを提供し、計画に基づいたプロモーションを可能にしました。このプロジェクトを通じて確かな「販売実績」が作られたことで、商品の信頼性が高まり、結果として百貨店などこれまで接点のなかった新規販路からのオファーや、ECモールへの展開挑戦につながっています。
学べるポイント
この事例は、ノウハウ不足を外部エキスパート(キュレーター)との協創で補い、緻密な広告宣伝戦略を確実に実行することの重要性を示しています。キュレーターによる具体的なマイルストーン設定や、SNS活用方法に関する実践的なアドバイスをプロジェクトの準備段階から実行することで、目標達成を確実なものにできました。さらに、成功の結果、外部パートナーへの依頼が承認され、ページ制作の準備期間が大幅に短縮されるなど、効率的かつ継続的な広告宣伝戦略の実行体制が資産として社内に構築されたことも、多くの企業にとって重要な示唆です。
事例2:家電メーカー小泉成器の新機軸「カルスイ」「かんまかせ」が切り拓いた共感型プロダクト戦略
基本情報
- 支援総額:約1,600万円(スティッククリーナー「カルスイ」)/ 約2,900万円(酒燗機「かんまかせ」)
- 支援者数:5,000人以上
- プラットフォーム:Makuake
成功の要因分析
家電メーカーの小泉成器が、従来の製品告知とは一線を画すアプローチで大きな成果を上げた事例です。成功の原点は、準備段階で商品スペックの訴求に終始せず、開発コンセプトやプロセスそのものを丁寧に言語化し、共感を醸成することに注力した点にあります。
特筆すべきは、ニッチ市場である酒燗機「かんまかせ」が約2,900万円という驚異的な支援額を獲得した点です。
通常の販売チャネルでは伝えきれない製品背景や開発者の想いを、プロジェクトページで丁寧に説明できるMakuakeの特性を最大限活用した結果、SNSで話題となり、市場規模が限られる製品であっても熱狂的な支援者を獲得できることを実証しました。
学べるポイント
製品の機能や性能だけでなく、「なぜこの製品を作ったのか」「どんな想いで開発したのか」というストーリーを丁寧に伝える重要性でしょう。特にニッチな製品ほど、その価値を理解してくれる濃いファン層にしっかり届けることが重要であり、Makuakeのようなプラットフォームは単なる資金調達の場ではなく、製品の「物語」を届ける最適な舞台になり得ます。
7)失敗しないために。宣伝活動における2つの注意点

宣伝活動を進める上で、陥りがちな失敗とその対策を知っておくことも重要です。以下の2つの注意点を必ず押さえておきましょう。
費用対効果は検証する(広告費の無駄遣いを防ぐ)
SNSの積極的な運用や広告は費用が発生します。
どの宣伝方法を活用するにも、発信の結果どんな影響があったか、かけた費用に対して見合っているか、見合っていない場合どう改善するか、などをこまめに確認・検討することが重要です。
対策- 各施策ごとにKPIを設定し、定期的に効果測定を行いましょう。例えば、SNS広告であれば「1支援あたりの獲得コスト」、インフルエンサー施策であれば「投稿からのプロジェクトページ流入数」などを追跡します。
- X(旧Twitter)はアナリティクス機能が発達しており、どれだけの人数にリーチできたか、そのうちいいね機能などに反応した人数はどれくらいの割合か、などを確認することができます。日々の数値の変動を小まめに確認し対策を行うことで、効果検証をよりスムーズに行うことが可能です。
問い合わせ急増・炎上リスクに備える(事前の体制準備)
宣伝を通じてより多くの人に接触するからこそ、予想を越えた反響や思わぬ炎上、クレーム対応などにつながる場合があります。これらに対応するためには、こまめに発信した内容を確認することや事前に準備をした上で発信を行うようにしましょう。
対策- 問い合わせ対応マニュアルを事前に作成し、想定される質問への回答を準備しておきます。
- プロジェクト公開直後は特に問い合わせが集中するため、この期間は対応できる人員を確保しておきましょう。
- SNS上でのネガティブなコメントには、感情的にならず、事実に基づいて冷静に対応することが重要です。誠実な対応は、むしろ信頼を高める機会にもなります。
8)クラウドファンディングの宣伝に関するQ&A

クラウドファンディングの宣伝について、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 宣伝にかける費用はどれくらいが目安ですか?
プロジェクトの規模や目標金額により異なりますが、一般的には目標金額の10%〜を宣伝費用として見込むことが推奨されます。例えば、目標金額が1000万円であれば、100万円程度です。
ただし、初めてのプロジェクトで予算が限られている場合は、まず無料でできる施策(SNS運用、友人・知人への告知、コミュニティへの参加など)を徹底的に行い、必要に応じて少額の広告費からテストを始めることをおすすめします。
Q2. 無料でできる宣伝方法だけで目標達成は可能ですか?
可能です。実際に、SNS運用と口コミだけで大きな成功を収めたプロジェクトも数多く存在します。特に、商品自体に強い魅力があり、ストーリーに共感を生む力がある場合、無料の宣伝方法でも十分に目標達成できます。ただし、無料の施策は効果が出るまでに時間がかかる場合が多いため、公開の1〜2ヶ月前から継続的に取り組むことが重要です。また、ターゲット層が明確で、かつニッチな市場の場合は、関連コミュニティでの丁寧な関係構築が非常に効果的です。
Q3. プレスリリースはどこに送れば良いですか?
プレスリリースの送付先は、大きく分けて以下の3つのアプローチがあります。- 配信サービスの利用: 「PR TIMES」などのプレスリリース配信サービスを利用すると、登録されている数千のメディアに一斉に配信できます。Makuakeなどのプラットフォームでは「PR TIMES」と提携を結んでおり、プロジェクトにまつわるプレスリリース配信がお得になるプランなどもあります。
- 個別メディアへの送付: 自社のプロジェクトと親和性の高いメディア(業界専門誌、ライフスタイルメディア、地域メディアなど)をリストアップし、記者の問い合わせフォームやメールアドレスを調べて個別に送付します。
- 記者との直接的な関係構築: 可能であれば、プロジェクト前から関連分野の記者と関係を築き、個別に情報提供することで、取材につながる可能性が高まります。
最も効果的なのは、上記を組み合わせて、広くリーチしつつ重要なメディアには個別アプローチすることです。
【まとめ】行動こそが成功への唯一の道

ここまで、クラウドファンディングの宣伝について、15の具体的な打ち手と成功事例を交えて解説してきました。最後に、この記事の要点を振り返りましょう。
- 準備期・公開中・終了後のフェーズごとに適切な宣伝を実施し、初速の重要性を理解して必要なリーチ数を逆算する
- 無料施策(SNS、口コミ、コミュニティ)を徹底し、有料施策は費用対効果を検証しながら実施する
- 支援者をファンに変える丁寧なコミュニケーションを、プロジェクト終了後も継続する
完璧な計画よりも、まずは行動してみることが重要です。
この記事で紹介した15の打ち手の中から、あなたが今すぐできることを一つ選んで、今日から始めてみてください。その一歩が、プロジェクト成功への扉を開きます。
アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」では、多くの実行者とサポーターが出会い、新しい価値を生み出しています。Makuakeはクラウドファンディングの仕組みを活かしたサイトとして、単なる資金調達の場ではなく、「応援購入」という新しい文化を創造しています。
初めての方も安心して取り組めるよう、プロジェクト設計から実行まで専門スタッフがお手伝いします。まずは無料の資料請求から、お気軽にお問い合わせください。
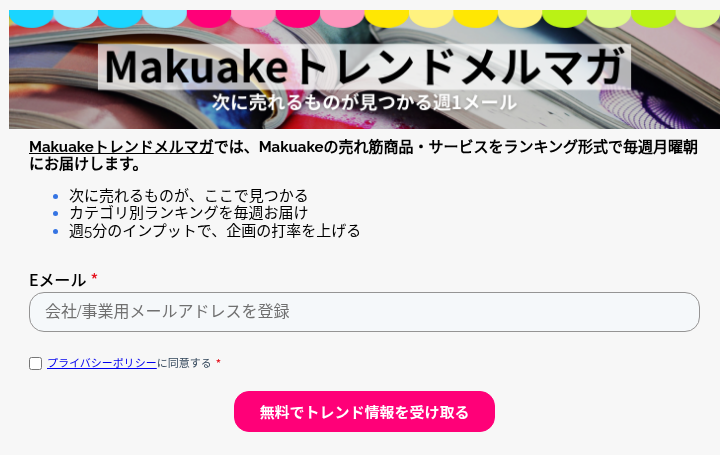
 By
By